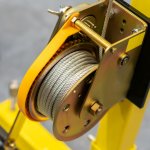私たちが生活する住宅を始めとして、駅や学校、オフィスビルや商業施設まで、私たちの生活の大部分は建物の中で行われています。
建物は雨風をしのぐだけではなく、私たちを自然災害から守るシェルターとしての役割もあります。
すべての建物は「建築士」の設計によって建設され、「建築士」の設計ひとつで建物の快適性や安全性はもちろん、商業施設としての価値まで大きく左右されます。
今回は、そんな重要な役割を担う「建築士」の仕事内容や年収、転職市場での人気などについて解説していきます。
この記事を読んでいただければ、「建築士」の資格の魅力やその将来性まで理解することができます。
建築士になりたい方、あるいは転職を検討している建築士の方にとって、とても有益な情報ですので、ぜひ最後までお付き合いください。
・公開 / 非公開求人多数掲載!
・転職後に収入380%の実績アリ!
・アドバイザーによるサポートも充実!
トントンでは様々な方に向けた求人を多数掲載!
初めての就職やキャリアアップのために適した企業に、
全て無料で応募可能です!
サイト掲載不可の
限定求人をご紹介!
目次
建築士の仕事内容とは?

建築士の代表的な業務範囲として下記が挙げられます。
- 基本設計
- 実施設計
- 確認申請
- 工事監理
基本設計
クライアントと共に建築の基本構想を考える業務になります。予算に合わせて建物のボリュームや基本仕様を決めていきます。
商業施設の場合は集客数の想定をし、投資物件は収益性の検討をします。住宅であれば、延べ床の坪数や間取りや外観の方向性などを決めていきます。
この段階ではまだラフなプランになりますが、大枠で建築関連法規に適合しているかのチェックも重要な仕事です。
実施設計
基本設計が終わったのち、法に適合させるための細部の設計をしていきます。建物内で健康に過ごすための環境面と、人命を守るための防災面からのチェックが必要となります。
工事業者に施工内容を伝達するための設計図はこの段階で作成します。
確認申請
建築基準法や都市計画法に適合した建物であることを自治体に認証してもらう作業が「確認申請」です。
民間の建築の場合は指定確認検査機関へ実務が委託されており、そちらと協議を行います。防災上の基準に関しては消防署との協議が必要です。
また、一定の規模以上の建物は耐震強度や省エネ性能に関して「適合性判定」という専門技術者の計算による検証が必要となります。
法適合の認証が得られると「確認済証」が発行され、建築工事の着工が可能となります。
工事監理
工事が着工しても、建築士の仕事はそれで終わりではありません。設計図通りに現場が施工されているかをクライアントの代理人としてチェックする業務が工事監理です。
無事に工事が終了し、確認審査機関や消防のお墨付きを得ると「検査済証」が発行され、建物の使用が可能となります。
建築士の仕事のやりがい

建築士の仕事のやりがいとは何でしょうか?
- 裁量がとても大きい
- 自分の仕事が数十年先も残る
- 協働作業による充実感と達成感の共有
といったことが挙げられます。
自分のアイデアや、経験から得た知見によってクライアントを納得させることができれば、その中での建築士の裁量はとても大きいものです。
実施設においては、描いた図面の線が現実の建築となり、場合によってはその後数十年に渡って残ることもあります。ひとつひとつの物件が高額であるため、非常に責任が重大な仕事です。
建築の設計から工事まで、クライアント・会社の同僚・官公庁・建設業者・現場職人など、多くの人との協働作業になります。
各々とのコミュニケーションに成功し、皆が同じベクトルを向いたときの達成感・充実感は何にも代えられないものがあります。
建築士の仕事の苦労

逆に、建築士の苦労にはどんなことがあるでしょうか?
- 対人折衝の多さ
- 長時間労働になりがち
- 工事現場とクライアントの板挟みによるストレス
といったことが挙げられます。
建築士の仕事の苦労としては、コミュニケーションが密であることによる対人折衝の多さでしょうか。
全員が納得できるひとつの解答を導けることは稀です。決まった正解が無い仕事のため、プロジェクトが進行しながらも常に不安を抱える傾向があります。
完璧を求めると、必然的に長時間労働となってしまうジレンマもあるでしょう。
図面が完成し工事現場が始まってからも、現場からの突き上げやクライアントからの変更要望や官公庁と協議との板挟みとなりがちで、ストレスも大きい仕事です。
それでも、最終的には建築という形となって具現化する達成感は、なかなか他の職業では味わえないものがあります。
設計したひとつひとつの建物が街をかたちづくり、将来の世代へと引き継がれていきます。
社会にとって必ず必要で、決して無くなることの無い安定性の高い職業です。
建築士の資格取得について

建築士の資格の種類と受験の概要について説明します。
建築士の資格には種類がある
建築士には、下記の種類があります。
| 一級建築士 | 全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理を行うことができます。 |
| 二級建築士 | 比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。 |
| 木造建築士 | より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。 |
さらに資格取得者が一定の経験を積み講習を受けることにより、上位資格を得ることができます。
| 構造設計一級建築士 | 一定規模以上の建築物の構造設計への関与が義務付けられています。 |
| 設備設計一級建築士 | 一定規模以上の建築物の設備設計への関与が義務付けられています。 |
| 管理建築士 | 建築士事務所を管理する建築士で、ひとつの事務所に専任で必ず1人必要です。 |
建築士は誰でも受験できる資格ではなく、受験するためには一定の条件が必要となります。
一級建築士の受験資格
- 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者
- 二級建築士
- 建築設備士
二級建築士・木造建築士の受験資格
- 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者
- 建築設備士
- 7年以上建築に関する実務を経験した者
建築士試験の難易度
令和3年度の試験結果は下記の通りです。
| 資格 | 合格率 | 受験者数 |
|---|---|---|
| 一級建築士 | 9.9% | 31,696人 |
| 二級建築士 | 23.6% | 23,513人 |
| 木造建築士 | 33.0% | 731人 |
特に一級建築士は、合格率が1割を切る難関資格です。
試験は設計手法や法規知識を問われる学科試験と、与えられた設計要件を基に一定時間で図面を書き上げる製図試験に分かれており、それぞれ異なる対策が必要な特殊な試験形態です。
学科試験をパスした者が、製図試験へと進むことができます。
例年のスケジュールですと、4月上旬に受験申し込みを行い、7月に学科試験が実施されます。8月末〜9月上旬に学科試験の合格発表があり、合格者に対して9月末〜10月上旬に製図試験が実施されます。
独学で建築士試験に合格は可能?
国家資格である建築士は難関資格であり、時間を掛けての周到な準備が必要です。
初学者が一級建築士に合格するためには、一般的に1000時間を超える学習時間を要すると言われています。二級建築士の場合は300時間程度が目安です。
資格取得に向けては、下記のような学習方法があります。
1.独学
初学者が市販のテキストを用いて独学で合格するのは、大変難しいです。
なぜなら、学科試験は4択問題であるため過去問の研究で十分対策が可能ですが、製図試験は一級は6時間半、二級は5時間という限られた時間で要件を満たし法規に適合した図面を描き上げるとても過酷な試験です。独学では時間内での図面の完成さえもおぼつかないでしょう。
また、独学では受験に向けての学習スケジュールも掴みづらく、モチベーションの維持も大変です。
2.通信教育
通信教育による添削指導で、独学の弱点をカバーすることも有効です。
費用もリーズナブルですが、学習の質と量を確保できるかは本人のモチベーション次第であることが難点です。費用の目安としては10万円未満です。
3.WEB講座
経験豊富な講師が動画や音声で解説する質の高い講義が受けられます。資格専門学校に通うよりも費用が大幅に抑えられますが、通信教育と同様の学習量確保の問題は残ります。
費用相場は通信教育と同等で10万円未満です。
4.資格専門学校
基本的には校舎に通学し、学科は講師による講義、製図は図面を見てもらいながら講師の直接指導を受けられます。模擬試験も豊富で、徹底した試験対策が用意されています。
また、目的を同じくするメンバーと切磋琢磨しながら学習を進められるのは大きな魅力です。
ただし費用は高額となり、学科だけでも30〜40万円、製図試験対策まで含めると60〜80万円程度の費用が掛かります。
建築士定期講習と資格取得後の各種講習制度

建築士定期講習
建築士法の規定により、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられています。参加することにより、法改正などについての最新の情報を得られます。
定期講習を受講しないと建築士免許が失効する訳ではありませんが、大手企業や官公庁物件では定期講習終了証の提示が求められ、業務を行う際の前提条件となります。
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士
これらの上位資格は、一級建築士として5年以上構造設計あるいは設備設計の業務に従事した後、専門の講習課程を修了することによって取得できます。
管理建築士講習
建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計などの業務に従事した後、管理建築士講習の課程を修了することによって取得できます。
建築士の年齢と性別の構成は?女性にとって働きやすい?

建築士の世代別年齢構成と男女比率について説明します。
建築士の年齢構成比
国土交通省の調査によると、建築士事務所に所属する建築士の人数は約14万人です。
そのうち、50代以上が全体の60%以上を占めています。逆に20代・30代の建築士の比率はわずか12%に留まっています。
高齢世代の大量引退を控え、現在30代以下の若年層の建築士は今後希少な人材となります。
建築士の男女構成比
令和3年度一級建築士試験の最終合格者の男女比率は男性が70.4%、女性が29.6%でした。
女性の合格は3割弱にとどまっていますが、建設業界全体がそもそも男性比率が多い業界です。
参考:公益財団法人建築技術教育普及センター 試験結果(一級建築士試験)
参考:公益財団法人建築技術教育普及センター 試験結果(二級建築士試験)
女性建築士の活躍
令和3年度の二級建築士試験の最終合格者は女性が37.2%と増加しており、女性の参入が増えてきています。
建築士には丁寧で繊細なクライアント対応や慎重な図面照合が求められるため、本来は女性に向いている仕事です。今後はさらに女性が活躍する余地が多くある業界だと言えます。
住宅業界では女性建築士が多く活躍しています。マイホームの新築を検討するのは子育て世代が多く、子育ての悩みを共有する女性ならではの、間取りや家事動線などのアドバイスが期待できるからです。
また、スーパーマーケットやショッピングモールなどの女性が多く利用する商業施設は、女性が設計したほうが気遣いが行き届き、利用しやすいという評価を受ける傾向があります。
女性を対象としたカムバック求人も多数
出産を機に建築業界を一度離れた女性を対象としたカムバック求人も多くあります。
長時間労働の代表格で女性から敬遠されてきた建設業界も、子育て中の女性が働きやすいようにフレックスタイム制やリモートワークを導入する企業も増えています。
男性が中心の建設工事現場も、男女別の仮設トイレが当たり前になるなど、女性がストレスを感じないための配慮が進んでいます。
建築士の年収はどれくらい?

建築士の年収と休日、他の資格との組み合わせた年収アップの方法について説明します。
建築士の年収(給料)の平均値
厚生労働省の調査によると、令和3年度の一級建築士の平均年収は586.1万円でした。
| 従業員10人以上の企業 (建築技術者) | 従業員1000人以上の企業 (建築技術者) | 全産業合計 (参考) | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 5,861.5千円 | 6,993.7千円 | 4,893.1千円 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.1歳 | 43.4歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 | 14.4年 | 12.3年 |
| 月間所定内実労働時間数 | 170時間 | 165時間 | 165時間 |
| 月間超過実労働時間数 | 17時間 | 24時間 | 11時間 |
| 月間給与額 | 393.6千円 | 451.5千円 | 334.8千円 |
| 年間賞与額 | 1,138.3千円 | 1575.7千円 | 875.5千円 |
国家資格だけあって、全産業平均と比較すると高収入な職業であると言えます。ただし、同じ建築士であっても対象とする分野や企業規模によって収入は大きく違います。
建築士の労働時間は?休日はどれくらい?
建築士の労働時間は、法人相手と一般消費者相手で内容が大きく変わってきます。
住宅などの一般消費者を対象とする業務は比較的図面量が少ないですが、クライアントとの打ち合わせ回数が多く、夜訪やクレームの休日対応は当たり前の業界慣習があります。
法人相手の場合は計画的に業務を進めやすいですが、施工規模が大きくなるとそれだけ技術知識が必要とされ、図面量も膨大になりがちです。官公庁との折衝にも時間が掛かるでしょう。
かつては長時間労働が常態化している業界でしたが、近年はリモートワークの推進や工事現場も含めての完全週休二日制の導入など、遅ればせながらワークライフバランスを取る動きが大企業を中心に加速しています。
建築士にはどんな人が向いている?

建築士という職業に向いている人の特徴は何でしょうか?
対人コミュニケーションが苦にならない人
建設業は人との関わり無しでは成立しません。クライアント・同僚・官公庁・建設業者・現場職人など多数の人との協働作業となり、協調性が求められます。
自分の意見を通すためには、根回しとマメなコミュニケーションが必要とされます。
細部への気配りができる人
建築士にはプロジェクト全体を俯瞰しつつ、最終的な着地点を間違わないための舵取り能力が求められます。
多くの協力者を動かしつつクライアントの意向を置き去りにしない、細心の気配りも必要です。
倫理観と公正性がある人
建築士は国が認めた建築関連法規の専門家です。法令を遵守する倫理観と、隠し事をしない公正さが求められます。
建築士と相性の良い資格は?

建築士と他資格との組み合わせにより、さらなる収入アップの相乗効果も考えられます。
1. 施工管理技士
建設工事の専任技術管理者として、工事現場の規模により専任で常駐が必要となります。
昨今の人材不足と相まって、近年大きな需要があります。
2. 宅地建物取引士
デベロッパーの立場から、基本計画の立案に関わる建築士が必要とされます。
法規上の制限をクリアにし、正確なボリュームチェックができる知識と提案力が求められます。
3. 行政書士
官公庁折衝のプロフェッショナルとして、特に開発行為に関わる土地区画整理事業の場面では大きな力を発揮します。
4. マンション管理士
区分所有に関する専門知識を持ち、マンション管理組合をクライアントとする大規模修繕計画の策定などにニーズがあります。
タワーマンションの老朽化問題など、今後活躍の場がますます広がる分野です。
5. 不動産鑑定士
公示地価の算出や競売物件の鑑定評価など、不動産の価値を算出する業務を行うのが不動産鑑定士です。
建築基準法の知識が求められるのはもちろん、鑑定評価にあたっての調達コストの算出や既存物件の修繕費の算定に建築士としての知識が必要とされます。
一級建築士を超える難関資格ではありますが、双方の資格の組み合わせは大変希少です。
転職市場での建築士の求人は人気ある?

厚生労働省発表の令和4年6月の有効求人倍率は「建築・土木・測量技術者」の職種で5.94倍となっています。
全職種の有効求人倍率では1.23倍ですので、建設業界全体が人材不足であり、その中でも建築士は難関資格ならではの希少性が高く評価されていると言えます。
参考:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和4年6月分)について
建築士の将来性は?今後発展する分野は?
建築士の将来性と、今後発展が見込まれる建築士の業務分野について説明します。
1. 資格保持者の希少化
先述のように、現在の最ボリューム層である50代以上の建築士の引退が今後控えており、大きな世代交代が起こります。建築士の資格保持者はますます必要とされ、安定性のある職業です。
AIによる設計の実証研究も進められていますが、高額な不動産を任せるに足る能力をAIが身に付けるのは当分先のことになります。対人コミュニケーションによる建築士の業務はこの先も続くでしょう。
2. リノベーション・解体設計需要の増加
スクラップ&ビルドによる建物の更新ではなく、構造躯体を生かして用途変更するなどの「リノベーション」が増加しています。
新築だけではなく、今あるものを活かした柔軟な設計力が求められるようになります。
また、アスベスト問題やリサイクルの厳格化により、慎重な解体作業が要求される時代となっています。建築とは逆の手順で建物解体を計画する「解体設計」も需要が増えている分野です。
3. 大規模災害を想定した防災対策
今後想定される南海トラフ地震などの被災を想定した「免震構造」など、建築による防災対策はますます重要となります。
自然災害から守るシェルターとしての建築の役割は、将来にわたって無くなることはないでしょう。
4. 再生可能エネルギー・省エネルギー・ZEH/ZEB対応
地球温暖化対策としての温室効果ガスの削減に建築は大きな影響を及ぼします。
太陽光発電システムなどの設置により再生可能エネルギーを利用しつつ、高効率設備の導入や断熱性能の強化により省エネルギー化を進めた建物はZEH/ZEBと呼ばれ、国を挙げて推進されています。
エネルギー分野での建築士の取り組みも、今後さらに求められていく分野です。
5. DX対応・BIM(三次元設計)分野の拡大
他業種に比較して対応が遅れていたDXについても、急速に発展しています。
設計業務においてはペーパー図面がタブレット上でチェックできるのは既に常識となっています。
一部では実行されていますが、二次元設計からBIMによる三次元設計へ移行し、設計図面と現実の工事現場との食い違いを無くす設計手法が今後の標準となっていくでしょう。
まとめ
ここまで、建築士の資格の概要や仕事内容、年収や将来性について説明してきました。
今後、資格保持者の高齢化が進み建築士の人材不足が問題となることが予想されます。
これから取得を検討している方には大きなチャンスがありますので、建築士資格取得へチャレンジすることをおすすめします。
また、建設業界では業務の多様化やDXの進行、女性の進出による業界地図の激変も進行中です。
建築士の資格をお持ちの方も、常に最新の知見を得てクライアントからの多様な要望に対応できることが、転職市場で求められるポイントです。
「トントン」は建築関係専門の求人サイトです。「建築士」についても様々な求人をご用意しています。
建築関係に特化しているからこそ、ご紹介できる求人がたくさんあります。無料で簡単に登録できますので、まずはあなたのご希望をお聞かせ下さい。